【公務員志望必読】就職偏差値が高いって本当?公務員になるメリット・デメリット

記事更新日 2024年07月19日
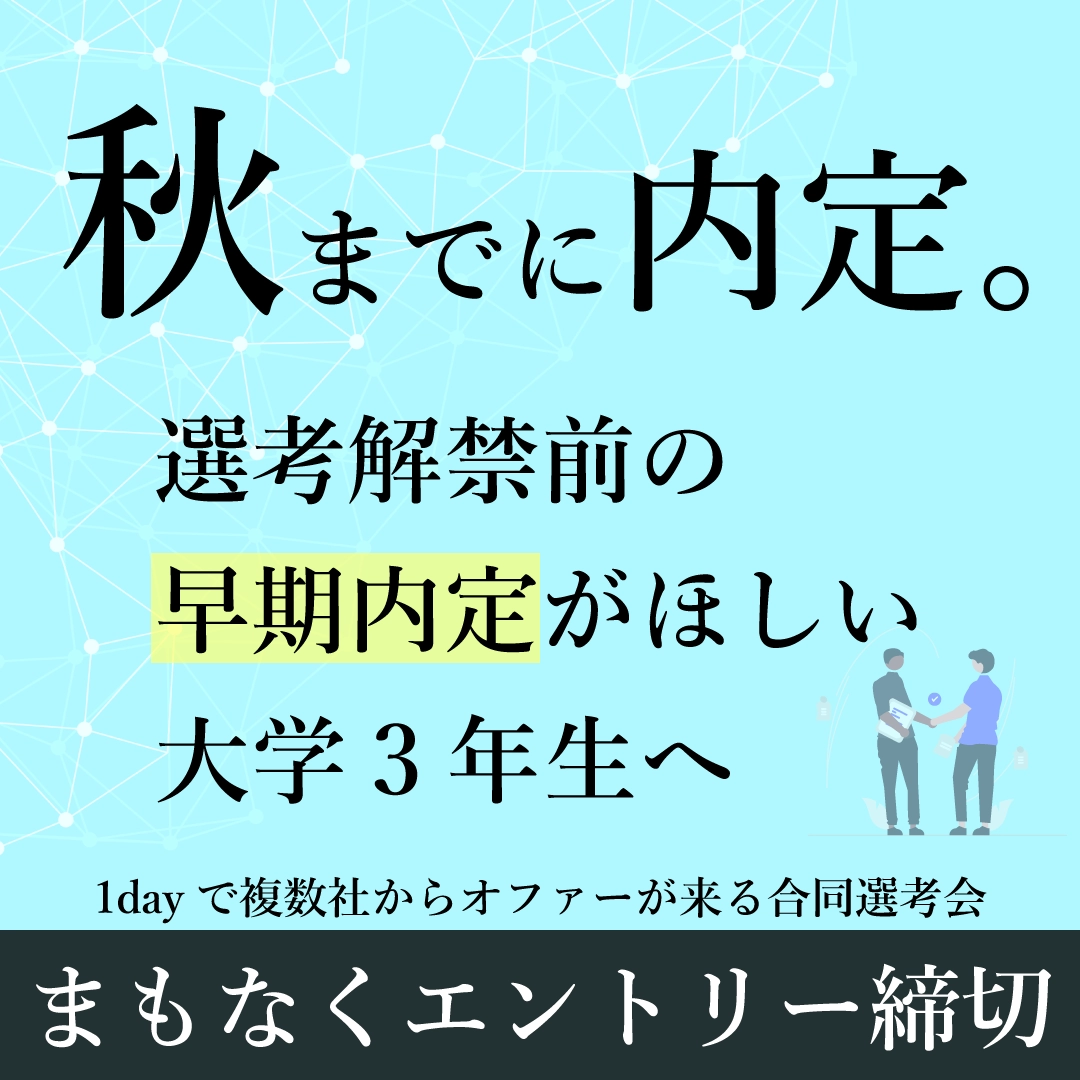
この記事内容の監修者

- ジョブトラ編集部
- ジョブトラアカデミー編集部です。 早期内定をサポートする、リアルな体験談やコラムを発信しています。
「民間企業、公務員、違いはよくわからないけど安定してそうな公務員になれればいいかな」
「就職偏差値が高いといえば、安定の公務員でしょ。不景気に強いって親も言ってたし。公務員試験を受けるから、就活はしないでおこう」
って、思っていませんか?
今「ギクっ」と思ったあなた。
今回はあなたのような方に、民間企業と公務員にはどのようなメリット・デメリットがあるのか、ざっくり理解してもらうための記事になっています。
当然のことですが、公務員になるためには採用試験に合格しなければいけません。
地方公務員であれば都道府県・市町村などが実施している試験です。
就職活動をしている中、同時並行で公務員を目指す場合、試験対策にはかなりの時間を費やすことになります。
それも踏まえて、民間企業への就活をある程度削りながらも、公務員を受けるメリット・デメリットを語っていきます。
結論から書きますが、公務員になるメリットは、以下の3つです。
1.給与・雇用が安定している
2.全国転勤が少ない
3.地方公務員は定時で帰れることが多い
地方公務員になるメリット1.給与・雇用が安定している
公務員はとにかく給与が安定しています。
公務員の給与は、民間企業の平均賃金に合わせて賃金調整されているものです。
ですが、最近10数年の民間企業と公務員の平均賃金を比較すると、公務員の方が高いという結果が出ています。
さらに、公務員は雇用が安定しています。
公務員には倒産やリストラがまずないため、ほとんどの場合は定年まで働くことができます。
賃金・雇用が安定していることで得られるメリットはたくさんあります。
まず、将来設計が立てやすくなります。
結婚や出産、マイホーム購入などのライフイベントを、計画的に実行できるのです。
2つ目は社会的信頼が高いという面です。
これはローンが組みやすくなるといったことが例として挙げられます。
社会的信頼が厚いほど、将来設計も確実なものになってきますよね。
地方公務員になるメリット2.転勤が少ない
地方公務員は圧倒的に転勤が少なく、基本的には各地方の都道府県の役所に勤めることが多いです。
そのため、自分が働きやすい環境で働くことが可能です。
これが民間企業の総合職になると、全国転勤はあって当然。
数年単位で生活スタイルが変わりえます。
それに対し公務員は転勤が少ないため、自分にとって好都合な環境で働くことができます。
そのため、「実家の傍で暮らしたい」「家を建ててずっと住みたい」といった方には、ストレスも感じずに働くことができます。
地方公務員になるメリット3.定時に帰りやすい
地方公務員の場合、基本的には8時30分〜17時15分(休憩1時間)が勤務時間になります。
総務省自治行政局の調査によると、地方公務員の残業時間は、月に13.2時間と記載されています。
月22日勤務だと仮定すれば、一日の残業時間は約1時間と考えられます。
(この結果がリアルな数値を反映されているかはなんとも言えないところですが…)
この情報をもとに考えると、残業時間を含めても18時頃には帰れる試算に。
これだけ早く帰ることができれば、家庭や趣味などの自分の時間を十分に確保することができますね。
参考:総務省自治行政局 「 地方公務員の時間外勤務に関する実態調査結果 」より
これらを踏まえると、公務員の安定性、継続性を考えて「就職偏差値が高い」というのは誤りではないでしょう。
就職偏差値が高い?公務員になるデメリットは年功序列と副業禁止規定
メリット同様、デメリットも公務員はハッキリしています。
1.成果を出しても給与は変わらない
2.副業が禁止されている
地方公務員になるデメリット1.成果を出しても給与は変わらない
公務員は給与が安定している反面、成果を上げても成果報酬は支払われません。
毎年ほぼ一定の昇給が加算されていくだけです。
公務員は国や自治体で定められている給料表に基づいて給与が支払われています。
ですから、どれだけ周囲の職員より頑張って良い成果をあげたとしても、支払われる給与は同じなのです。
地方公務員になるデメリット2.副業が禁止されている
公務員には副業禁止規定があります。
副業禁止は、国家公務員法や地方公務員法によって定められています。
副業がバレてしまった場合には、厳しい処分が課せられます。(※1)
【営利企業への従事等の制限】
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
政府からも副業を推進される時代です。
社会人になったら、何かしらの副業をやることになるだろうと考えていても、公務員では副業はできません。
参考: 「地方公務員法」より
就職偏差値が高くても……公務員を安易に選ぶのはやめよう
ここまで、地方公務員のメリット・デメリットを紹介してきました。
地方公務員の給与は安定していて労働環境が整っている反面、成果が反映されず年度の昇給以外で給与アップは望めない。
というのがざっくりとした公務員の説明でした。
あなたはどのように感じましたか?
安定していてライフプランが立てやすいと思ったら、公務員に向いているかもしれません。
逆に、バリバリ働いた対価は欲しいと思った方は民間企業向きかもしれません。
親が「安定しているから」と勧めてきたから、あるいはネットで「就職偏差値が高いのは公務員」などという言葉に流されて、安易に公務員一択で就活を終えようとしていませんか。
自分がどうよなキャリアを積んで、どのような人生を送りたいかで、公務員・民間企業をそれぞれ志望するのか変わってきます。
今一度、自分で考えてみてください。
27卒向け:無料で選考対策できる就活イベント
大手企業のインターンや本選考で取り入れられている難解なビジネスゲームを実践できる 唯一の就活イベントです。
事前準備不要、ありのままでビジネスゲームを実践することで本質的な強みを5つの項目で数値化 することで自己分析やESにも役立ちます。
- 延べ12万人が受講した就活イベント+最大7社企業説明会
- 大手選考を体験できる対面型ビジネスワーク
- 参加企業からのフィードバック&オファー
この記事内容の著者

- ジョブトラ編集部
- ジョブトラアカデミー編集部です。 早期内定をサポートする、リアルな体験談やコラムを発信しています。

