学生が知っておくべき「潰れない会社」のポイント

記事更新日 2024年07月19日
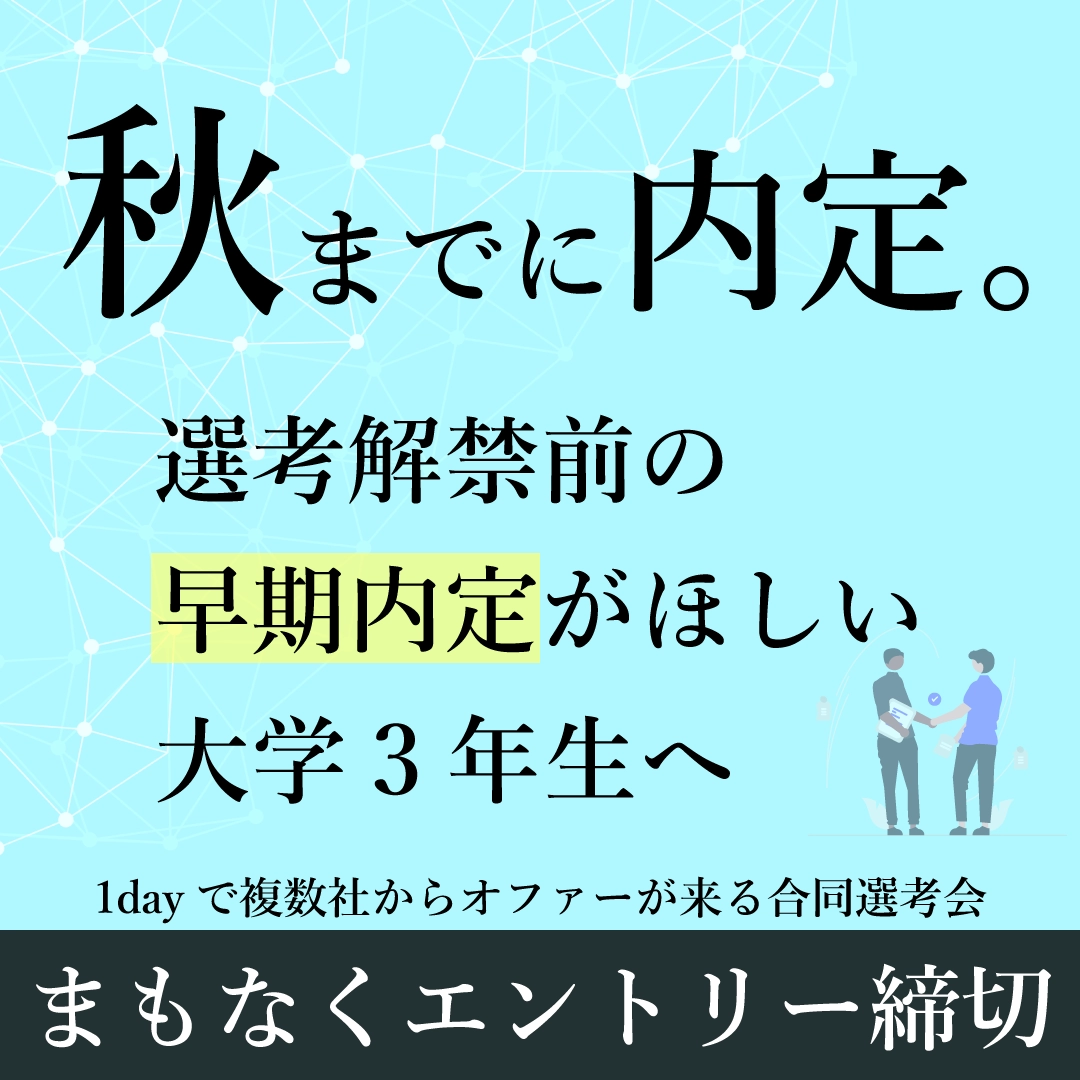
この記事内容の監修者

- ジョブトラ編集部
- ジョブトラアカデミー編集部です。 早期内定をサポートする、リアルな体験談やコラムを発信しています。
こんにちは。かねどーです。
今回の記事では、過去2回行ってきたファイナンス分析の知識と法律や歴史の知識を組み合わせながら、潰れない会社とはどういう会社か、またどういう会社に入れば損をしなくて済むかを考えてみましょう。
なおこの記事は、読者が企業の財務諸表や四季報等を自分でチェックできる前提で書いていますので、不安な方は過去記事を先にご覧ください。
たくましく生きるためのファイナンス分析① なぜファイナンスを学ぶのか
たくましく生きるためのファイナンス分析② 就活生・転職者が本当に見るべき指標(大企業の場合)
会社が潰れるとは何か?そのパターンについて
まず大前提として、会社が潰れるとは何を指すのかを正確に知っていますか。ここの理解によって企業ニュースの理解度が変わりますので、学んでいきましょう。
倒産には大きく分けて「清算型」と「再建型」の2つがあります。
清算型とは、企業に残っている資産を債権者=お金を貰う権利がある人、に配分したのちに会社を消滅させる手続きで、法的には破産とか特別清算といった処理になります。
ただし、会社には従業員もいれば取引先もおり、多くの場合では再建可能性があれば再建しようという力学が働くため、例えば親会社グループが事業の撤退を判断したような場合を除けば大企業ではあまり発生しません(パナソニックプラズマディスプレイはこのケースです)。
対して再建型とは、会社のハコやブランドを残したまま、お金の支払や返済を伸ばしてもらったり経営陣を入れ替えたりしながら、経営を立て直して再起を目指す手続きです。
法的には民事再生法や会社更生法の手続きになります。
会社が残るので「倒産」のイメージにはそぐわないかもしれませんが、事実上経営のギブアップ宣言であり、破産や清算に準じる扱いを受けます(ニュースではよく「経営破綻」という言い方をします)。
有名な例だと、JALやウィルコムが行っていますね。
これらには含まれないものの、事実上倒産とみなされるケースもあります(手形の不渡りを2回起こして、銀行取引を停止された場合など)。
どのパターンにせよ、大規模なコストカットやリストラ等従業員にも大きな痛みを強いることになるので、避けられるのであればそれに越したことはありません。
以下では様々な観点から、潰れない会社を見分けるためのポイントを押さえていきましょう。
ファイナンス観点で見た危険な企業
企業の倒産リスクを財務観点から見たときに、学生でも容易にチェック可能なのは以下のような指標です(粉飾決算の可能性等については、ここでは一旦考えないものとします)。
これで赤信号が出る会社は、どんなに有名な会社や大々的に宣伝している会社でも、学生にはおすすめしません。
貸借対照表:流動比率(流動資産÷流動負債)
これは、流動負債(支払い義務がすぐに訪れる負債)と比較して、流動資産(現金や、短期で現金化できる資産)がどれだけあるかを示す比率です。
100%を割っている場合、相当安定確実な現金収入がない限りは赤信号です。
損益計算書:当期純利益(額)
私の記事ではおなじみ純利益。
スタートアップでもないのに当期純利益が3期も4期も連続で赤字の場合、赤信号です。
これくらい赤字が続くと株主や金融機関、取引先等の態度も変わりますので、まともな資金調達ができず取引条件も悪化し、倒産につながる場合があります。
キャッシュフロー計算書:営業キャッシュフロー
「黒字倒産」という言葉がある通り、例え会計上の純利益が黒字であっても、資金繰りに困って倒産する企業はあります(興味がある方は、アーバンコーポレーションの倒産事例について調べてみてください)。
キャッシュフロー計算書を見ることで、損益計算書からは見えない直接的な現金の出入りを確認することができます。
例えば、不動産会社が土地や建物を沢山仕入れてきたがさっぱり売れない、というような状態を考えてみましょう。
経営的には非常によくない状況ですが、帳簿上は現金が不動産という別の資産になっただけなので、まだ損益にはほぼ影響がありません。
このような状態にある企業のキャッシュフロー計算書を見れば、棚卸資産が大幅に増加し、たとえ黒字であっても営業キャッシュフローが悪化しているはずです。
これも3期以上連続赤字なら赤信号でしょう。
さて、ここまで当記事を読んでくださった聡明な読者はこう思うかもしれません。
「財務諸表を公開していない会社はどのように判断すればいいんだ?」と。
いいですか。
財務諸表を公開していない会社に、潰れない会社なんてありません。
そうした会社(外資系企業やスタートアップ等の非上場企業)は、他の会社でいつでも転職できるだけのスキルや経験を積み上げてから入るか、まぁ潰れてもなんとかやっていくぞという覚悟を決めてから入るものであって、潰れない会社に入りたい人向けのものではないので今回はあまり語りません。
以下の記事で詳しく書いておりますので、ご興味がある方は読んでみてください。
たくましく生きるためのファイナンス分析① なぜファイナンスを学ぶのか
業界再編等の流れは見逃さない
以上のような財務的分析に加えて、特定の業界を目指す時には「業界地図等」の業界全体を網羅した本をパラ読みし、その業界における再編・統合の流れをよく見ておきましょう。
例えば銀行、保険、小売業界等が典型的ですが、合併・買収を繰り返して上位企業がどんどん中下位を吸収しているような業界は、そうしなければやっていけない状況にあることが普通です。
こうした業界でポジションが確立できていない中下位の会社に就職する場合、倒産と言わないまでも合併等により、会社の目指すところや業務環境が著しく変わる可能性を覚悟した方がいいと思います。
潰れない会社を目指すべきか?
ここまでは潰れない会社、吸収されない会社の見分け方についてお伝えしました。
しかし特にここ最近の経済変化はめまぐるしく、30-40年の長い目で見ると、潰れない会社はないと思っておいた方が良いかもしれません。
またキャリアチェンジ、就労環境への不満、経済的理由、心身の不調など、倒産に限らず転職活動を始める理由は色々あります。
皆さんの大半は、どこかのタイミングで転職活動をすることになるでしょう。
であれば、はじめから転職を考慮に入れたマインドの方がのちのち良いかと思います。
「今やっている仕事や判断は、転職活動をする時にはどのように説明できるか?」という観点で自分の仕事を見直すと、仕事のクオリティアップにもつながります。
安定志向を持つ就活生の皆さんにおかれましても、是非就職後も自分のキャリアについて内外の機会を見続けてみてください。
27卒向け:無料で選考対策できる就活イベント
大手企業のインターンや本選考で取り入れられている難解なビジネスゲームを実践できる 唯一の就活イベントです。
事前準備不要、ありのままでビジネスゲームを実践することで本質的な強みを5つの項目で数値化 することで自己分析やESにも役立ちます。
- 延べ12万人が受講した就活イベント+最大7社企業説明会
- 大手選考を体験できる対面型ビジネスワーク
- 参加企業からのフィードバック&オファー
この記事内容の著者

- ジョブトラ編集部
- ジョブトラアカデミー編集部です。 早期内定をサポートする、リアルな体験談やコラムを発信しています。

